
小誌は、その象徴のひとつ、2005年発表のRM 009のアルシック製ケースの製造現場を取材する僥倖に恵まれた——それから10年以上。この間、リシャール・ミルの内外装の素材と複雑機構のアーカイブが着々と増えてきたのは言うまでもない。その中で際立っているのが、リシャール・ミル氏の〝新しいもの〟や〝時計の世界に存在しないもの〟に対する鋭敏な嗅覚である。先述のアルシックを採用したRM 009しかり、近年最も話題をさらった野心作であり、文字通り革命作でもあるサファイアクリスタルケースを採用したRM 056しかり、その開発姿勢を見ていると、〝できるか、できないか〟ではなく、〝やるか、やらないか〟であることが分かる。もちろん、ミル氏の行動規範は明らかに後者であり、やるからには、決して妥協は許さない。
一例を挙げれば、リシャール・ミルの複雑時計を手掛けるAPルノー エ パピのジュリオ・パピ氏は、かつてこう述べた。「依頼品の完成を開発に関わったスタッフたちと喜んでいると、ミル氏から電話があり、いきなりダメ出しをされた揚げ句、さらに高い次元の内容を要求された」といった類いのエピソードは、開発された〝作品〟が後に伝説的なピースになったものほど、よく耳にしたものだ。ミル氏自身が、時計師でもエンジニアでもない門外漢であるが故に、その道のエキスパートほど、技術的あるいはコスト的に尻込みしてしまう障壁を、ミル氏は決してそうとは認識しない。だが、それは決して〝無知〟から来る〝無謀〟ではなく、どんなに時間とコストがかかっても、やるかどうかの覚悟を現場の開発者や時計師たちに問うているに過ぎないのだ。
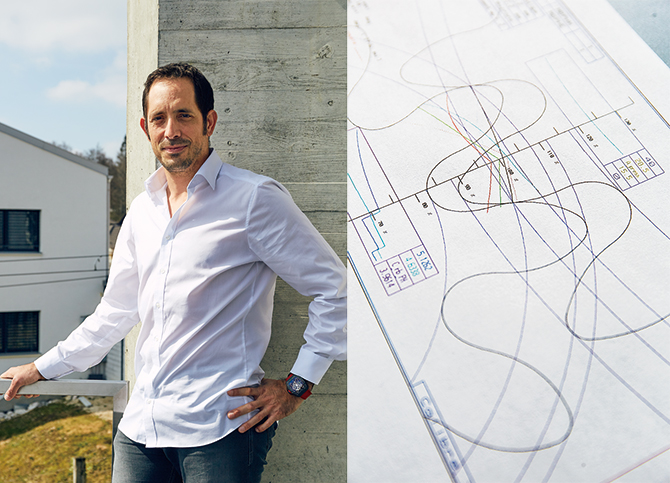
その証拠に、無謀だと思われたパイプでムーブメントを支持する構造を持つRM 012や、ブシュロン創業150周年を記念して製作した合成サファイアの地板と半貴石を埋め込んだ歯車を持つ「オマージュ・ア・ブシュロン」RM 018など、困難を極めるものほど、彼は決して妥協せず、逆に、常にプロジェクトに関わる開発者たちの〝職人魂〟に火を付けることで、最終的に成し遂げてきた。そのために費やされた時間とコストは、すべてその作品の価値として付加され、結果、リシャール・ミルというブランド自体の価値をも劇的に高めることに貢献してきたのだ。今年の新作も、すでにメンズのトゥールビヨンにおいてサファイアクリスタルケースの実績があったとはいえ、女性向けに、しかもピンクに染め上げたサファイアクリスタルケースを採用するなど、凡庸な常識人では考えもしないことだ。
2012年、RM 056のサファイアクリスタルケースの製造を担ったステットラーを取材した際、その大きさを満たすサファイアクリスタルケースを成形するために必要な結晶の巨大さやその製法、それを加工する難しさと途方もなく低い歩留まりに驚愕したものだったが、投資を含めた物理的・人的・時間的コストをすべて回収できたのは、リシャール・ミルがそういう〝本気〟のブランドだと、すでに高級時計市場において広く認識されている何よりの証しでもあるのだ。










