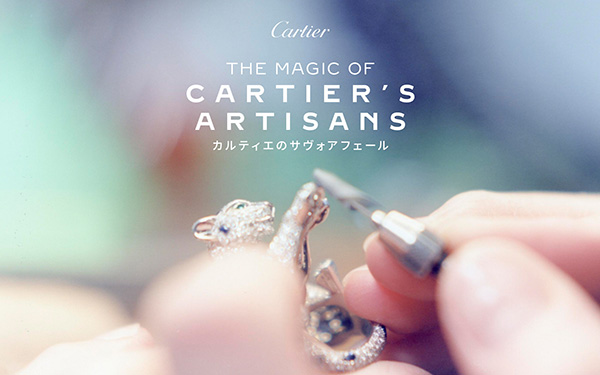時計専門誌『クロノス日本版』編集部が取材した、時計業界の新作見本市ウォッチズ&ワンダーズ2025。「ジュネーブで輝いた新作時計 キーワードは“カラー”と“小径”」として特集した本誌でのこの取材記事を、webChronosに転載する。今回は、特集のタイトルにもなった小径ケース、そしてカラフルな文字盤にフォーカスして、このトレンドを振り返る。
Photographs by Ryotaro Horiuchi
広田雅将(本誌):取材・文
Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)
Edited by Yuto Hosoda (Chronos-Japan)
[クロノス日本版 2025年7月号掲載記事]
アンダー40mmは当たり前に 小径ケースの躍進
ここ数年、局地的に目立ってきた小さなケース。今年は多くのメーカーが小径に目を向けるようになった。共通するのは、デフォルメのないデザイン。つまり、男性用の時計をそっくり縮めた時計が主流となったのである。何が変化をもたらしたのか?

今年の白眉は、直径34mmサイズの「1815」だ。その小ぶりなケースは初代1815を思わせるが、搭載ムーブメントは初代のCal.L941(直径25.6mm)から28.1mmに拡大された。それに伴い、パワーリザーブは45時間から72時間に延長された。また、ケースサイドの処理が示すように、厚さ6.4mmのケースながら、巧みに立体感を加えている。男性のみならず、女性も使える新世代のドレスウォッチだ。
2017年から時計業界を風靡した、いわゆる“ラグスポ”のブーム。この定番化を受けて、一部の時計愛好家たちは、違うジャンルに目を向けるようになった。それがレザーストラップを備えたドレスウォッチである。かつて地味だったこのジャンルは、ラグスポが進化させた立体的な造形や、さまざまなカラーにより、一度はドレスウォッチから離れた層や、ラグスポで時計の世界に触れた顧客を魅了するだけの装いを獲得した。その先にあるのが、小さなケースだ。

インヂュニアに加わった新サイズ。写真が示す通り、40mm版をそっくり縮小したデザインを持つ。バックル側のブレスレット幅は13mmと、今風にテーパーは強め。しかし、ヘッドとテールのバランスが良いため、腕なじみに優れている。汎用性の高い実用時計だが、パワーリザーブが短いのは惜しい。
なぜ今年小さなケースが目立ったのか。各社の説明はまちまちだが、理由はいくつかに絞られる。そもそも、薄いクォーツ時計やスマートウォッチに親しんだ若い層は小さく薄い時計を選ぶ傾向がある。加えて時計市場を牽引してきた団塊世代(ベビーブーマー)ジュニアも大きな時計を忌避しつつある。小径化は当然の帰結だろう。

女性用の傑作、Cal.9S27を搭載した新作。直径30mm、全長36.2mmというサイズは明らかに女性用だが、針やインデックスのデフォルメを抑えた結果、男性でも使えるデザインとなった。また厚みを10.5mmに抑えたのも、今のトレンドに即している。左のサントス同様、さじ加減のうまさが光る1本だ。
もうひとつの理由が、金価格の高騰だ。金時計を作るにしても、サイズが小さければコストは抑えられる。各社は決して公言しないが、製造コストとラグジュアリーを両立させる最適解は、確かに小さなケースになるだろう。
面白いのは、新しいスモールモデルの在り方である。かつてこういったモデルは、視認性を高めるために、文字盤や針がデフォルメされていた。しかしここで挙げた4モデルが示すように、最近はメンズサイズをそのまま縮小したデザインが目立つ。女性だけでなく、男性にも使ってもらうための配慮だろう。さておき、今後ますます、小さなサイズは広まりを見せるに違いない。

男性、女性を分けることなく、時計を作るようになった今のカルティエ。それを象徴するのが、「サントス ドゥ カルティエ」に加わった小径サイズだ。デザインは既存のモデルそのままだが、サイズを縮小し、ケースを薄くするためあえて秒針を省いている。また、完成度を高めるため、あえてコマ調整機能も省かれた。
“ポストラグスポ”の最旬トレンド 拡充する中間色ダイアル
ここ10年で最も変わったのは、ラグスポでも複雑時計でもなく、文字盤だろう。技術の進化と、カラフルな文字盤を打ち出したスマートウォッチの普及は、かつて地味だった時計の色に、多彩な表現を与えるに至った。中でも注目すべきは、明らかな個性を持つ中間色だ。発色の難しいこれらの色は、今や当たり前の存在になりつつある。

“ラグスポ”の穴を補完するように拡大するドレスウォッチ(とベーシックウォッチ)。その鍵となったのは、新しい文字盤の色だ。かつてブルー、ブラック、シルバーしか存在しなかった文字盤の色は、2015年以降、明らかにそのバリエーションを増やした。グリーンやいわゆるサーモンカラーが恒例だろう。
そして今や各社は、新しい文字盤表現に挑むようになった。そのひとつが、オーデマ ピゲやグランドセイコー、オリエントスターにシチズンなどが取り組む構造色。もっとも、コストが高いこの文字盤を採用できるメーカーは、今後も限られるだろう。
むしろ目立つのが、今まで発色が難しいとされてきた中間色だ。こういった色味は、安定させるのが困難なため、採用はごく一部の限定モデルに限られていた。しかし、グランドセイコーやパルミジャーニ・フルリエ、ノモス グラスヒュッテなどは、差別化の手法として積極的に中間色を使うようになったのである。しかもウブロに至ってはセラミックスで中間色を実現し、しかも時計全体の色味を合わせてしまった。10年前では考えられない離れ業だ。
かのロレックスでさえも、今や差別化の手法として中間色を使うようになった。厚いラッカー仕上げを得意とする同社は、まず発色の難しい赤や黄色に取り組み、続いては、より難しいニュアンスカラーを採用するに至った。
しかし、最も注目すべきは、中間色を表現したH.モーザーだ。単に石を合わせただけではないセンスは、文字盤表現で他社をリードする同社ならではのものだ。