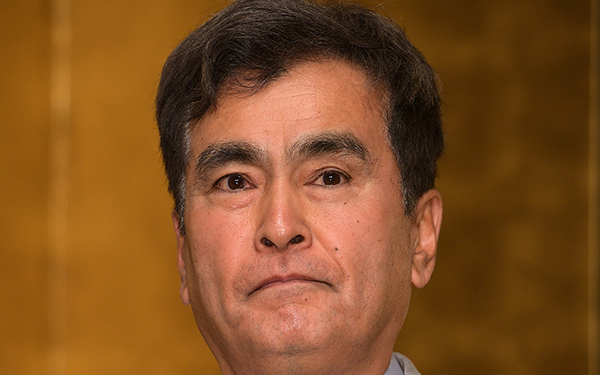テクノロジーの分野で知らぬ人はいないほどのジャーナリストが、本田雅一氏だ。その本田氏が、ウェアラブルデバイスについて執筆する本連載。今回は米国の老舗、ガーミンによるハイエンドスポーツ、「Fenix 6x Pro Dual Power」について語る。

太陽電池式マルチスポーツGPSウォッチ。パワーリザーブ最大21日間(スマートウォッチモード使用時)。FRP×Ti(直径51mm、厚さ14.9mm)。直径1.4インチディスプレイ。10気圧防水。13万円(税別)。
Text by Masakazu Honda
ガーミン「Fenix 6x Pro Dual Power」
今やアウトドア、スポーツのジャンルで他に類を見ないほど腕時計メーカーとして成功を収めているガーミンだが、90年代にその成功を予想したものはいなかったはずだ。
ガーミンというブランドに初めて出会ったのは1998年、テクノロジー企業を訪ねる取材で米国に出かけた時のこと。エレクトロニクス製品の専門店チェーン、Fri’s Electoronicsを訪問し、ハンドヘルド型GPSデバイスの「eTrex」を買い求めた。
現在もガーミンの製品ラインナップに残るeTrexは、山登りやトレッキングといったアウトドアに革命をもたらした製品だ。解像度の低いモノクロ液晶ながら、どこにいても自分の位置と向かっている方向、進んできた経路を確認できるという装置である。
このeTrexこそがガーミンのスマートウォッチの原点でもある。GPS(全地球測位システム)の開発に携わったエンジニアが中心になって生まれたガーミンが、初めて開発したポータブルデバイスがeTrexだったのだ。
そのeTrexが進化し、腕時計型になり、さらには用途が広がっていった。そう考えれば、現在のガーミン製品の位置付けが明確に浮かび上がってくる。

明確な意思が込められた設計
スマートウォッチと言えば、Apple Watchやwear OS採用スマートウォッチをまずは想像することだろう。これらの製品はスマートフォンを身にまとう感覚の製品だ。しかし、ガーミンの作るスマートウォッチはもっと自律的で、目的志向が強い特定用途向けにさまざまな情報を提供するだけでなく、時にはその行動や体調を予測してアドバイスをしてくれる。
「Fenix 6x Pro Dual Power」シリーズは、その中でも最も多くの用途が盛り込まれた製品だ。ディスプレイサイズの違いにより、6S/6/6xという3つのシリーズがラインナップされている。
今回試用したのは42mmディスプレイのFenix 6x Proだが、バッテリー容量とディスプレイサイズを除けば、どの製品も電子機器としての能力や機能などに違いはない。
地図データなど込み入った情報を読み取りやすくしたいなら6x、男性向けのアクティブウォッチなら6、女性だけでなくランニングなどでの使い勝手を意識した小型ケースが好みなら6sと用途に応じて選べばいい。
実際に使い始めてみると、Fenix 6x Pro Dual Powerは、すぐにApple WatchやWear OS採用製品とは異なることが分かる。例えば操作性。
4つのボタンだけでの操作は、タッチパネルが当たり前の昨今、使い始めは戸惑うことが多いかもしれない。いや、そもそもタッチパネルに対応しないのは時代遅れではないか。そう感じる読者もいるだろう。
しかし、ガーミンのスマートウォッチはApple Watchに代表される典型的スマートウォッチとは異なる価値にフォーカスをしており、タッチパネル非対応はガーミンが狙う用途においてはむしろ利点にもなっている。
アウトドアやウィンタースポーツの中、グローブをはめたままの操作、あるいはランニング時にブラインドでの確実な操作。ガーミンが主戦場としているアウトドアやスポーツといった領域で頻繁に使っていると、その良さをはっきりと自覚できる。
“マルチだが深みもある”、掘り下げの深さが魅力
目的がはっきりしているからこそ、強い意志で明確な商品企画を行っているからこそ「コイツでなければ」というユーザーの覚悟に呼応する深みがあるのだ。
反射型カラー液晶パネルやPower Glassと名付けられたソーラーパネルをラミネートした風防用強化ガラスの採用にも、そうした強い意志を認める。
反射型カラー液晶パネルは画質面では、OLEDやバックライト型カラー液晶パネルには遠く及ばない。しかしながら、アウトドアでの見やすさは格別だ。ディスプレイが消費する電力の大多数はバックライトであるため、バッテリー持続時間も長い。

ここにソーラーパネルを組み合わせることで、太陽光による継ぎ足し充電でさらに使用時間が延長される。
実はPower Glassのガラス基板はコーニングのGorilla Glass。これまでFenixシリーズの上位モデルにはサファイアクリスタルが使われていたが、太陽電池を効率よく機能させるためにはサファイアクリスタルが利用できない。
これを割り切りとみるか、進化のための選択と捉えるかだが、ガーミンは意思を持って太陽光によるバッテリー持続時間の延長を狙ったことになる。
強いLEDが必要となる心拍センサー、GPSによる軌跡記録を用いるスポーツ系スマートウォッチではバッテリー消費を少しでも抑えたいが、さらにそこに“エクストラの電源“を加えることが、ユーザー体験を高める上での重要と判断したのだろう。
Fenixシリーズは、数あるガーミンのスポーツウォッチが持つ機能をひとつに集約したマルチスポーツモデル。こうした製品は、ひとつひとつの機能が“薄まり”がちだが、どのスポーツへの対応でもトップクラスに掘り下げているのが何よりの魅力だ。
たとえば同社のスマートウォッチ「approach」シリーズはゴルフクラブのスイングとインパクトを検知し、GPS情報とともにひたすらに記録。別途用意されているゴルフコースの地図データを重ね合わせ、どのようにラウンドしたのかを振り返ることができる。
ゴルファー向けには、クラブに装着する専用外部センサーも販売されており、どのクラブで打ったのかまでを自動記録し、クラブの番手ごとに飛距離などの統計を取ることもできる。
筆者はゴルフを嗜まない人間だが、ゴルフ好きに尋ねるとapproachを導入して以来、ラウンドしているのが楽しくて仕方がないと異口同音に話していた。
他にもスキー、サーフィンといったアウトドアスポーツへの対応はどれも本格的で、マルチスポーツでありながらも、その機能には深みまである。
汎用のスマートウォッチでは代替できないことが強み
スマートウォッチが備える“スポーツ対応”、“活動量計測”は、それぞれの種目ごとにアスリートや競技志向のアマチュアのニーズには対応できない場合が少なくない。
ところがガーミンの製品は、もちろんヘルスケアやフィットネスの領域もカバーだけでなく、アスリートやそれに準ずる愛好者が求める機能をきっちりと組み込んでいる。

例えばランニング。“ランニングの記録と利用者へのアドバイス”という、ランナー向けの基本機能だけを比較しても、一般的なスマートウォッチより情報が豊富で見やすく、クラウドにデータをアップロードすれば、パフォーマンス向上と怪我を未然に防ぐためのトレーニング計画作りを手伝ってくれるが、そこで終わりではない。
オプションデバイスをシューズに装着することで、ランニングフォームの分析やアドバイスなども得られる。
さらにガーミン製品が得意なのが、地形情報を用いた各種機能だ。
例えばランニングであれば、あらかじめ登録しておいたコースのアップダウン情報をもとに区間ごとのペース配分をアドバイス。トレッキングやトレイルランでも高低差情報を取り込んだ機能や使用者へのアドバイスを行う。
その一方では、内蔵センサーを用いた実に細やかな機能も提供する。
Apple Watchにも搭載されている“転倒検出”をはじめとする生命の危機に瀕する事故を検出した際に緊急連絡先にメッセージを送る機能はそのひとつだが、そこまで検出できるのかと驚かされたのは筋力トレーニングを行っているとき、その種目を自動的に検出し、回数やインターバルのアドバイスをくれたことだ。
複数種目を組み合わせた種目は正しくは識別できないが、例えばベンチプレスやスクワットなどであれば、正しく認識した上で回数を数えてくれ、計測を終えてボタンを押すと自動的にインターバルの計測へと切り替わる。
種目は後からでも編集することが可能で、筋力トレーニングの履歴管理が極めて簡単に行えた。
ガーミンが提供するあらゆる価値を集約したFenix、Suicaにも対応
Garminは高級ラインのMARQをラインナップしているが、それらを除くあらゆるスポーツ向けスマートウォッチの頂点として位置されているのがFenixシリーズだ。万人に向けた製品には、専門性とも言うべき深さが足りないものだが、Fenixにはガーミンが提供しているさまざまなアスリートやプロフェッショナル、エンスージャスト向け製品の機能が、ほぼ漏れなく組み込まれている。
もちろん、あらゆる価値を集約しているだけに、特定用途向けにケースの意匠がデザインされているわけではない。しかし、各機能は間違いなくそれぞれのジャンルでトップクラスの評価を受けているものだ。この性能や機能に妥協しない“万能性”こそがFenixシリーズの最大の魅力だろう。
とはいえ、こうした万能性と深みのある機能は以前からずっと同じ。だからこそガーミンは存在感を高めてきたが、他にもスポーツやアウトドアに特化したスマートウォッチがないわけではない。
そうした中でガーミンが頭ひとつ抜けている理由はふたつある。
決済機能の「Garmin Pay」が日本のキャッシュレス決済インフラでも最も大きなシェアを持つJR東日本の「SuiCa」に対応していること。そして、日常のストレスも含めて使用者の身体の状態を推測するボディバッテリーといった分かりやすい指標を示してくれることだろうか。
Suicaへの対応は多くは語らないが、対応に苦慮するメーカーが多い中にあって、ほぼ日本でしか使われていないSuicaに対応した点は素直に評価したい。Suicaにさえ対応すれば、あらかじめ現金をチャージしておくプリペイドの決済ニーズにはほとんど対応できるからだ。
一方のボディバッテリーは、微妙な心拍の揺れなどから体へのストレスを検出。積算して行くことで、スポーツや日常の運動だけではなく、デスクワークなど心肺や筋肉に負荷をかけない作業での身体への負担を数値化している。

アウトドアやスポーツに特化した深みがあるのはもちろんだが、その上で日常時の使いやすさなども配慮している。
もうひとつはApple Watchと同様、プラットフォームとして機能していること。
ガーミンのインターチェンジャブルストラップ、Quick Releaseは極めてシンプルにストラップの交換が可能となっているのはもちろんだが、サードパーティー製ストラップも豊富で選択肢が多い。また音楽再生サービスへの対応もSpotifyだけではなく、日本向けにはLINE Musicに対応。2000曲までをダウンロード可能だ。
“機能の磨き込み”は将来の製品に生きる
さて、正直に告白するならば、ここまで絶賛するとは使い始めるまでは考えていなかった。もちろん製品の優秀性は知っていたが、ディスプレイのコントラストやボタンオンリーの操作、サードパーティー製アプリケーションが少ないことなど、いくつかのエクスキューズが思いついたからだ。
しかし使用を続けていれば、またガーミンが得意な領域を考えるならば、サイドライト付きの反射型液晶パネルを採用するのは当然であるし、樹脂を織り交ぜたハイブリッドのケース設計は、GPSの検出速度と精度を引き出すためだと考えれば、むしろ巧みに質感を高める工夫がポジティブに感じられる。
ガーミンの得意ジャンルは、アウトドアとスポーツに特化し、掘り下げた機能性、さらにはデータを分析、視覚化しつつ、ユーザーにアドバイスを提供するスマホアプリケーションとクラウドサービス、およびGPS関連機能だ。
そうした部分が徹底的に磨き込まれ、孤高の存在として追求を極めているところは、一部ユーザーは“やりすぎ”と感じるかもしれない。しかし製品において「やりすぎ」はないと断言しておきたい。
“ホンモノ”として磨き込んでいるからこそ、製品のオーナーは満足する。それは機械式腕時計の世界でも同じのはずだ。ただ、彼らは自らが得意な分野を極めようとしているだけ。この磨き込みへのこだわりが、次の製品、また次の製品と改善をもたらし、いつしか定番となって行くのだ。

テクノロジージャーナリスト、オーディオ・ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。1990年代初頭よりパソコン、IT、ネットワークサービスなどへの評論やコラムなどを執筆。現在はメーカーなどのアドバイザーを務めるほか、オーディオ・ビジュアル評論家としても活躍する。主な執筆先には、東洋経済オンラインなど。