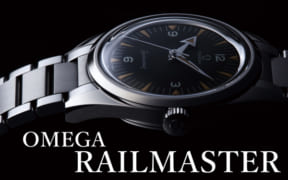2025年に新作が発表された「シーマスター レイルマスター」。正確な列車の運行を管理する鉄道員のために開発されたレイルマスターは、そのスピリットをいかにして最新モデルに反映させたのか。ブラウングラデーションダイアルを備えたスモールセコンドモデルの実機を基にレビューする。
Photographs & Text by Tsubasa Nojima
[2025年9月9日公開記事]
オメガの鉄道員向け耐磁ウォッチ、「レイルマスター」

オメガは1957年に、3つのスポーツウォッチを発表した。ダイバーズウォッチの「シーマスター300」、クロノグラフウォッチの「スピードマスター」、そして耐磁ウォッチの「レイルマスター」だ。シーマスター300はダイバー、スピードマスターはレーサーやパイロットなど、それぞれがプロフェッショナルに向けた特殊な時計という位置付けであった。レイルマスターは、磁気にあふれた電気式気動車を運用した鉄道員をターゲットとしたモデルであり、パイロットウォッチで培った耐磁性のノウハウと、シーマスター300譲りの防水構造を有した堅牢な手巻き式時計であった。
そんなレイルマスターの新作が、2025年に発表された。今やオメガを代表するコレクションに成長した同期のシーマスターやスピードマスターに対し、度々ラインナップに名を連ねるものの、あまり注目されてこなかったレイルマスター。復活を遂げた2000年代以降のモデルは、実質的に「シーマスター アクアテラ」のバリエーションであり、やや地味な印象が強かったためか、マイナーな存在であったことは否めないだろう。
新作のレイルマスターも同様に、ベースはアクアテラだ。しかし、オリジナルを彷彿とさせるディティールと、グラデーションカラーを組み合わせたダイアルは、レイルマスターらしさと現行機としてのモダンな風合いが見事に融合したものである。
1秒1秒を正確に管理し、列車を安全に運行させることが求められる鉄道員。一瞬の判断ミスは、そのまま大事故に直結しかねない。そんな彼らの手元で着実に任務をこなしていたレイルマスターは、現代のユーザーに何をもたらすのか、実機を手にしながらその魅力に触れていきたい。

2025年に登場した、新しい「シーマスター レイルマスター」。ブラウンのグラデーションダイアルを備えたスモールセコンドモデルを実機レビュー。自動巻き(Cal.8804)。35石。2万5200振動/時。パワーリザーブ約55時間。SSケース(直径38mm、厚さ12.36mm)。150m防水。95万7000円(税込み)。
名機「ランチェロ」風なスモセコダイアル
2025年に登場したレイルマスターには、グレーグラデーションダイアルのセンターセコンドモデルとブラウングラデーションダイアルのセンターセコンドモデルが存在し、それぞれにレザーストラップとステンレススティールブレスレットのバリエーションが用意されている。今回インプレッションを行うのは、ブラウングラデーションダイアルにステンレススティールブレスレットを組み合わせたモデルだ。
ダイアルのレイアウトは至ってシンプル。外周にはくさび型インデックスが並び、3時、9時、12時にはさらに丸みを帯びたアラビア数字のインデックスも配されている。6時位置には一段下がったスモールセコンドが与えられ、12時位置にはブランドロゴと“Railmaster”の文字がプリントされている。筆者の知る限り、オリジナルのレイルマスターにスモールセコンドモデルは存在しないはずだ。2000年代以降を見ても、ユニタスムーブメントを搭載した手巻きモデルくらいではないだろうか。そう考えると、レイルマスターというよりは、コレクターズアイテムとしても知られる「ランチェロ」の雰囲気に近いように感じる。
ドーフィン型の時針とアロー型の分針の組み合わせは、現行のオメガ「シーマスター アクアテラ」でも採用されているものだ。1957年のオリジナルは時針がアロー型、分針がドーフィン型であったため逆だが、時刻の読み取りにあたって違和感はない。
簡潔な要素で構成されたダイアルに個性を与えているのが、ヴィンテージ調のカラーリングだ。中央を明るく、外周に連れて暗くなるブラウンのグラデーションが、スモーキーでミステリアスな印象を与えている。時分針とインデックスには褐色の蓄光塗料が塗布され、経年によって変色した状態を再現している。蓄光塗料はぷっくりと塗られており、やや平面的なダイアルに立体感をもたらしている。

「アクアテラ」譲りの上品なケース
ツイストした短いラグ、幅と厚みを持たせたプレーンなベゼル、円錐形のリュウズを組み合わせたケースのデザインは、アクアテラと同じのようだ。サイズは直径38mmであり、ベゼルとラグの上面をポリッシュ、その他をヘアラインで仕上げている。
前作のレイルマスターも似たデザインであったが、アクアテラのラインナップには存在しない40mm径であったことや、全体をヘアライン仕上げで統一していた点が異なる。特に仕上げの違いは見た目の印象も大きく異なり、ツール感の強かった前作に比べ、2025年の新作ではより洗練されたように感じる。1957年のオリジナルがポリッシュを主体としていたことを考えれば、原点に近付いたとも取れる変更だろう。

ポリッシュの面に歪みはなく、特にベゼルは、まるで鏡のように周囲を映し出す。ケースサイドのような広い面でもヘアラインは均一に施され、エッジもしっかりと立っている。ポリッシュとヘアラインが交差するエッジがビシッと一直線にそろっていることも加え、オメガらしい仕上げの良さは、さすがと言うべきだろう。風防には、両面無反射コーティングを施したドーム型のサファイアクリスタルが採用されている。
ケースバックの外周には、ミドルケースにねじ込むための波型の溝が与えられている。シーマスターコレクションでお馴染みのデザインだ。中央にはサファイアクリスタルがセットされ、内部に搭載されたムーブメントを鑑賞することが可能。

ステンレススティール製のブレスレットは、ひとつひとつのコマが短い3連タイプ。可動域が大きく、しなやかに動く。調整用のコマは、両サイドからマイナスネジで連結されているタイプ。中央の1列のみポリッシュ仕上げとすることで、ケースの仕上げに調和した上品な印象にまとめられている。バックルは両開きのタイプを採用。片方が嵌合式、もう片方がプッシュボタン式だ。嵌合式の方にはセラミックス製の小さなボールが埋め込まれており、小気味よいクリック感を味わうことができる。
多くの両開きバックルでは構造上、微調整機構が備わっていないことが多いが、本作のバックルは、開いた状態でボタンを押下することで数mmだけ微調整を加えることが可能な「コンフォートセッティング」が搭載されている。ただし、微調整機構を用いて伸ばした状態でバックルを閉じると、少し不格好な隙間ができてしまう。


マスター クロノメーター認定のCal.8804
ムーブメントは、機械式自動巻きのCal.8804を搭載している。現行のオメガにおいて、シンプルな3針モデルの多くはCal.8800系またはCal.8900系を採用する。どちらもコーアクシャル脱進機とシリコン製ヒゲゼンマイを備えた、マスター クロノメーター認定の両方向巻き上げの自動巻きムーブメントであるが、前者はコンパクトなサイズにリバーサー式の巻き上げ機構、後者はツインバレルを採用したやや大きめのサイズにウィグワグ(スイッチングロッカー)式の巻き上げ機構を搭載している点が大きく異なる。
オメガのほとんどの現行モデルが取得するマスター クロノメーターは、精度だけではなく、耐磁性や防水性、パワーリザーブなどをケーシングした状態でテストする認証規格だ。テストはスイス連邦計量・認定局(METAS)によって行われている。貸与品のため、耐磁性や防水性を試すわけにはいかないが、少なくとも精度においては期間中の調整が必要なかったほどの優秀さであった。
ブリッジには、オメガを象徴するアラベスク調のコート・ド・ジュネーブが施されている。センターから放射状に広がる装飾が光を反射させる様子は、うっとりするような眺めだ。地板にはペルラージュが施されている。
癖のない操作感も魅力だ。本作はねじ込み式リュウズを採用しているため、最初にねじ込みを解除する必要がある。ねじ込みを解除した状態でリュウズを12時側に送ると主ゼンマイを巻き上げることが可能。防水用のパッキンがしっかり効いているのだろうか、少し重いが、チチチチチという音によってしっかりと巻き上げている感触を味わうことができる。そのまま一段引き出すと秒針が停止し、時刻調整が可能となる。
あえて気になったところを言えば、ねじ込みを解除した状態でのリュウズの飛び出しが少ないことだろうか。うっかりねじ込みを忘れて使用しそうになったことがあった。

個性的なダイアルを備えた万能機
本作は、特に手首に載せた時に真価を発揮する時計だ。直径38mmであることに加え、ラグからラグまでのケースの縦の長さが約45mmと控えめなため、手首回り16.5cmの筆者の腕にもバランス良く収まってくれる。滑らかなブレスレットは、装着感も上々だ。ただし、本作がややスポーティーな時計であることを考えると、バックルは両開きではなく、三ツ折れタイプの方がマッチしたのではないだろうか。あくまで個人的な好みであるものの、装着感よりも着脱の容易性を優先したいところだ。
やや小ぶりで重心も高くないためか、装着時に腕を振っても振り回されるような感覚は皆無。ひとつ気になったことを言えば、自動巻きローターの音が少し響くことだろう。長時間の着用でも疲れるようなことはなく、ビジネスシーンから休日まで、さまざまなシーンに寄り添ってくれるベーシックな実用機としての安心感がある。
ダイアルの視認性も良好だ。ブラウングラデーションダイアルとヴィンテージカラーのインデックスの組み合わせがコントラストに欠けるのではないかと危惧していたが、そんなことはない。アラビア数字インデックスは時計の向きを瞬時に把握しやすく、アロー型の分針は、1分単位での正確な読み取りを助けてくれる。
ストライプ状のパターンや立体的なインデックスを特徴とするアクアテラのダイアルと比較すると、キラキラとした輝きが抑えられている分、レイルマスターの方が視認性に優れる印象だ。もっとも、これはアクアテラの視認性が悪いというわけではなく、ふたつのモデルを比べた際の相対的な評価である。個性の立ったデザインと実用性の両方を求めるならば、レイルマスターはその筆頭候補となり得る存在だろう。

レイルマスターを定義するもの
耐磁ウォッチとして登場したレイルマスター。しかし、オメガのマスター クロノメーター化の波は、多くのモデルに強力な耐磁性を持たせ、そのアイデンティティーをコモディティー化してしまった。パソコンやスマートフォンをはじめ、電子機器が身近にあふれる現代において、耐磁性への重要度は1950年代と比較にならないほど高まっているということなのだろう。
思えば、他社の耐磁ウォッチも似たような運命をたどっている。ロレックスの「ミルガウス」は生産終了となって久しく、同社の現行のラインナップは、どれもがブルーパラクロムヘアスプリングやシロキシヘアスプリングによる高い耐磁性を獲得している。IWC「インヂュニア」は、複数回のモデルチェンジの過程で方針転換を繰り返し、今ではブレスレット一体型のいわゆるラグジュアリースポーツウォッチとして活路を見出した。
ではレイルマスターに残ったものは何か。それは、アラビア数字インデックスを配した、ノンデイト仕様のクリーンなダイアルに集約されているのではないだろうか。そのストイックなデザインには、1957年誕生時のプロフェッショナル向けツールウォッチとしての威厳が宿っている。先に挙げた2社を例にとれば、ミルガウスとインヂュニアよりもむしろ、「エクスプローラー」や「パイロットウォッチ マークシリーズ」に近い存在なのではないだろうか。
オメガというブランドの中に限れば、もはや“耐磁ウォッチ”というカテゴリ自体に意味はないだろう。しかし現行のレイルマスターには、1秒が命取りになるシビアな世界で社会インフラを支え続けた歴史的名機の血がしっかりと受け継がれているのだ。